Nursing care
column 介護コラム
リハビリテーションマネジメント加算とは?算定要件など詳しく解説!
投稿日:
高齢者が住み慣れた自宅・地域で暮らし続けるために必要な要素に、「身体機能の維持・向上」があります。それぞれの疾患や生活状況・身体状況に沿った、質の高いリハビリテーションを提供することを目的に設定されたものが「リハビリテーションマネジメント加算」です。
リハビリテーションマネジメント加算は、2021年と2024年のどちらの報酬改定でも見直しが実施されている加算です。本記事では、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件やポイントなどを解説します。
目次
リハビリテーションマネジメント加算とは?

リハビリテーションマネジメント加算とは、利用者一人ひとりに対し、質の高いリハビリテーションの提供と、その管理を目的として創設された加算です。
リハビリテーションマネジメント加算では、調査(Suvery)・計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)のSPDCAサイクルをもとにサービスが実施されます。
評価の対象となる項目は、利用者の状態や生活環境も考慮した計画書の作成、適切なリハビリの実施、計画の評価と見直しです。
直近の2024年の介護報酬の改定では、リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点などから、区分の見直しが行われました。
リハビリテーションマネジメント加算の介護サービス別単位数

リハビリテーションマネジメント加算を算定できるサービス種別は、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの2種類です。特に通所リハビリテーションでは、算定期間による違いなど単位数が複数あるため、注意しましょう。
訪問リハビリテーションの単位数
訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算は、以下の通りです。
- リハビリテーションマネジメント加算(イ):180単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ):213単位/月
- 医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合:(上記に加えて)270単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ・ロは2024年度の報酬改定で廃止されています。代わりに、利用者またはその家族が医師の説明に同意した場合、上記に加えて270単位算定できるようになりました。
通所リハビリテーションの単位数
通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算は、同意月から6カ月以内と、6カ月を超えた場合の2種類があります。単位数は以下の通りです。
【1】同意月から6カ月以内
- リハビリテーションマネジメント加算(イ):560単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ):593単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ):793単位/月
【2】同意月から6カ月超
- リハビリテーションマネジメント加算(イ):240単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ):273単位/月
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ):473単位/月
また、上記に加えて、訪問リハビリテーションと同様に以下の加算が算定可能です。
- 医師が利用者またはその家族に対して説明し、同意を得た場合:(上記に加えて)270単位/月
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件
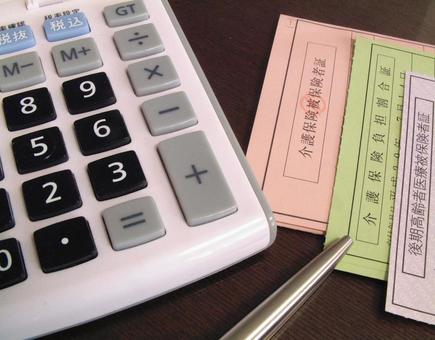
それぞれのリハビリテーションマネジメント加算を算定するためには、要件を満たす必要があります。2024年の報酬改定では廃止となった加算や、従来の内容を引き継ぎつつ、その内容に加えて新たな加算取得のために加えられた要件があります。
訪問リハビリテーションの算定要件
利用者のニーズの達成や、生活の質の向上のためには、提供するリハビリテーションの質そのものを向上させることが必要です。そのためには専門職種の配置や、それに伴う書類の整備などさまざまな要素があり、全てを満たすことで事業所も加算を算定できるようになります。
加算の算定が、結果として利用者や事業所に還元するような好循環を作ることが重要です。
訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件は、以下のような内容です。
【リハビリテーションマネジメント加算(イ)算定要件】※一部抜粋
リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件には、改定前のリハビリテーションマネジメント加算(A)イで設定された算定要件と同要件が設定されています。
- 医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。さらに医師の指示内容を記録すること。
- リハビリテーション会議(テレビ会議可(新設))を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること。
- 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画書を見直すこと。
- PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
- PT、OT又はSTが(指定居宅サービスの従業者と)利用者の居宅を訪問し、その家族(当該従業者)に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
- リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。
- 上記に適合することを確認し、記録すること。
算定要件の詳細は、下記厚労省通知をご参照ください。
参考:「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」
参考:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
【リハビリテーションマネジメント加算(ロ)算定要件】
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)の要件に適合すること。
- 利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
【リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合】※新設
改定前のリハビリテーションマネジメント加算(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。
- リハビリテーション計画について、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得る事。
通所リハビリテーションの算定要件
通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件は、以下のような内容です。
【リハビリテーションマネジメント加算(イ)算定要件】※一部抜粋
訪問リハビリテーションと同様に、リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件には、改定前のリハビリテーションマネジメント加算(A)イで設定された算定要件と同要件が設定されています。
- 医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。さらに医師の指示内容を記録すること。
- リハビリテーション会議(テレビ会議可(新設))を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること。
- 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画書を見直すこと。
- PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
- PT、OT又はSTが(指定居宅サービスの従業者と)利用者の居宅を訪問し、その家族(当該従業者)に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
- リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。
- 上記に適合することを確認し、記録すること。
算定要件の詳細は、下記厚労省通知をご参照ください。
参考:「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」
参考:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
【リハビリテーションマネジメント加算(ロ)算定要件】
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)の要件に適合すること。
- 利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
【リハビリテーションマネジメント加算(ハ)算定要件】※新設
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
- 事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行っていること。
- 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
- 利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
- 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。
【リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合】
改定前のリハビリテーションマネジメント加算(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。
- リハビリテーション計画について、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。
リハビリテーションマネジメント加算を得るためには「リハビリテーション計画書」が必要

より質の高いリハビリテーションを提供するためには、SPDCAサイクルにもとづいて、リハビリテーションを行う必要があります。利用者一人ひとりの状態や、生活状況に応じた計画書を作成し、その内容を実施、評価することで初めてリハビリテーションマネジメント加算が算定できます。
リハビリテーション計画書の概要
リハビリテーション計画書は、訪問、通所リハビリテーションを提供するに当たって、医師がリハビリを指示する際にその目的や方法などについて説明するための書類です。
利用者および家族のニーズや、生活における長期的な目標、それを達成するための短期目標については、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画書に記載されています。その目標を達成するために、リハビリテーション事業所としてどのような支援を提供していくのか明記するものになります。
具体的には、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえた上でのリハビリメニューの記載、利用者の希望、リハビリの目標や方針、リハビリの実施上の留意点などです。
リハビリテーション計画書は、目標の達成時期や設定した期間に応じて、定期的に評価と見直しを行います。計画を変更する必要がある場合は、介護支援専門員に情報提供を行います。
また、医学的管理を行っている医師やその他の居宅サービス事業者などにも、利用者の状態の変化などを適宜共有することが必要です。
リハビリテーション計画書の様式
リハビリテーションを実施する際、計画書を作成する必要がありますが、それぞれの事業所独自に様式を定め、作成していいわけではありません。リハビリテーション計画書の様式は、厚生労働省にて用意されています。
すべての事業所が、統一した計画書を使用してリハビリテーションを実施することは、計画書によるリハビリテーションのばらつきをなくすことにつながります。
また、万が一利用する事業所が変更となっても、ニーズや目標、ADLなど項目が統一された計画書を使用することで、利用者に提供するリハビリテーションの質を一定に保つことにつながります。
次の項目で計画書の項目について解説します。
リハビリテーション計画書の記載項目

リハビリテーション計画書には、それぞれ必要とされている記載項目があります。利用者の状態を捉え、個別に合ったリハビリを提供するために重要な項目です。
項目ごとのポイントを押さえておきましょう。
参考:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」
参考:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
本人や家族の希望
本人の希望に関しては、厚生労働省で設定している「別紙様式2‐1(興味関心チェックシート)」で把握した、利用者がしてみたい、または興味があると答えた内容を考慮しながら記載します。
家族の希望に関しては、利用者の家族が利用者に自分の力でできるようになってほしいことや、生活する上での理想とする状態像などを具体的に確認した上で記載していきます。
利用者が寝たきりで意向の確認が難しい場合などは、家族と面談しながら設定しましょう。
計画書を作成する側の主観や思い込みで記載することのないよう、注意が必要です。
健康状態・経過
原因疾病、当該疾患の発症日・受傷日、直近の入院日、直近の退院日、手術がある場合は手術日と術式などの治療経過、合併疾患の有無とそのコントロールの状況など、これまでのリハビリテーションの実施状況(プログラムの実施内容、頻度、量等)を該当箇所に記載します。
日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準にはそれぞれ自立度を記載します。
心身機能・構造
評価基準の各項目について、現在の状況・活動への支障がある場合には該当項目を選択します。また、該当項目にない項目に関して障害を認める場合は、特記事項に記載をします。
6分間歩行試験、TUG Test、MMSE、HDS-Rについては評価した値を記載しましょう。測定値を記入するとともに、将来の見込みについて該当箇所もチェックします。
服薬管理の状況については、現在の状況と将来の見込みを該当箇所にチェックします。
コミュニケーションの状況については、現在の状況を記載するとともに、将来の見込みを該当箇所にチェックします。
活動
活動の評点については、リハビリテーション計画の見直しごとに、以下の通り、各活動の状況の評価を行い記入します。
- 基本動作
居宅を想定しつつ、基本動作(寝返り、起き上がり、座位保持、立ち上がり、立位保持)の状況を評価し、該当箇所にリハビリテーション開始時点および現在の状況について記載します。 - 活動(ADL)(Barthel Indexを活用)
「している」状況について評価を行い、リハビリテーション開始時点および現在の状況について該当箇所に記載します。
リハビリテーションの目標や方針
目標は長期目標と短期目標(今後3カ月)を記載します。方針についても、短期目標と同様、3カ月の期間どのような方針でリハビリを実施していくのか明記しましょう。その他、本人や家族への生活指導の内容を、自主トレーニングの内容と併せて記載していきます。
この目標などの項目は、利用者や家族に説明し理解してもらう必要があります。中には、一度の計画書の説明では理解できなかったり、説明を忘れてしまう場合もあります。
利用者が分かりやすく、後々見返しても理解できるように専門用語の使用はできる限り避けて表記・表現するように心がけることが重要です。
リハビリテーション計画書を作成する際の注意点

リハビリテーション計画書を作成する上で、注意しなければならない点が3つあります。
1つ目が、介護支援専門員などが行う、利用者の生活全般におけるケアマネジメントと、リハビリテーション分野のマネジメントに相違がないようにすることです。
利用者や家族には、生活における課題や、かなえたいニーズがあります。それぞれのマネジメントで、ばらつきや方向性の違いがあると、課題解決やニーズの達成ができず利用者に不利益が生じてしまいます。
それぞれの専門職種で、利用者の捉え方やマネジメントの方向性、目標などを共有することが計画書を作成する上で重要です。
2つ目が、多職種連携との情報共有です。リハビリテーション計画書を作成しても、それが自らの事業所のみでとどまっていては、利用者の生活の質の向上にはつながりません。
利用者に携わる全ての事業所に、リハビリの内容や目標、注意点など計画書を通して情報を共有することで、統一した視点で利用者を捉えることや、変化に早く気づくことにつながります。
3つ目が、書類の保管期間です。計画書には2年の保管指示があります。作成した計画書の期間が終了したからといって処分してしまうのではなく、規定期間は利用者ごとに書類をまとめて、運営指導などで開示が求められた際には提出できるようにしておきましょう。
まとめ

利用者に質の高いリハビリテーションを提供するためには、利用者の状態をしっかりと捉えた上で、計画に沿って機能訓練を実施する必要があります。また、報酬改定の流れにもあるように「利用者の状態の維持」は機能訓練だけではなく、栄養面や口腔機能面など、さまざまな分野と関連して支援していくことが必要です。
質の高いリハビリテーションを提供し加算を算定することは、利用者の「目標」を達成するだけでなく、職員の自信にもつながります。リハビリテーションの質の向上だけでなく、事業所の収入の増加も目指していきましょう。
「まもる君クラウド」では、通所・訪問リハビリテーション事業所向けのソフトがあり、リハビリテーションマネジメント加算に必要な計画書の作成や管理はもちろん、請求業務や他の加算管理などの業務も一体的に行えます。日々の業務負担の軽減や、加算算定の効率化などメリットも多いため、介護ソフトをまだ導入されていない事業所は利用を検討してみてはいかがでしょうか。