Nursing care
column 介護コラム
国保連請求(介護保険請求)のやり方や流れは?注意点も紹介
投稿日:
介護業界で勤務していると、「国保連請求」という言葉を耳にすることがあります。
介護保険では、利用者に提供したサービスの対価を「介護報酬」として受け取る仕組みになっており、その報酬の一部を国保連に請求します。これを「国保連請求」と呼びますが、手順や流れが複雑で請求業務に不安を感じている人も少なくありません。
今回は、国保連請求について詳しく解説します。記事を参考にし、請求業務に関する不安を解消しましょう。
目次
国保連請求(介護保険請求)とは?

介護保険にかかる費用のうち、利用者の支払う自己負担分を除いた残りの費用は、公費(税金)と介護保険の被保険者が納める保険料でまかなわれます。公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が4分の1ずつ負担しています。
利用者が何らかの介護保険サービスを利用した際、その費用の1〜3割を自己負担としてサービス事業所に支払い、サービス事業所は残りの7〜9割を国保連に請求。審査を受けた後、支払いを受けます。これが国保連請求(介護保険請求)と呼ばれるもので、請求には期日や必要書類などが設定されています。
請求書類に不備がある場合や、期限内に必要書類を提出できない場合は報酬が支払われない事態も考えられるため、正確に請求業務を行わなければいけません。
国保連合会とは?

「国民健康保険団体連合会」は、国民健康保険法第83条に基づき、保険者(都道府県・市町村・国民健康保険組合)が会員です。設立には都道府県知事の認可が必要で、全国47都道府県にそれぞれ設立されています。国保連合会は、保険者である市町村から委託を受け、介護給付費などの審査や支払いをはじめとした請求業務を行います。
また、保険給付の支払いだけでなく、利用者などからの介護サービスの利用に対する不満や苦情・相談などにも対応するほか、苦情申立書の提出により調査を行い、事業者などに対してサービスの改善のために指導・助言する業務も担っています。
介護保険の目的とは?

日本では高齢化が進み、総人口に占める割合は2024年9月15日時点で29.3%という数値です。高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。
こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが「介護保険制度」です。全ての高齢者がサービスを利用しながら、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。
参考:総務省「統計からみた我が国の高齢者」
介護保険の仕組み
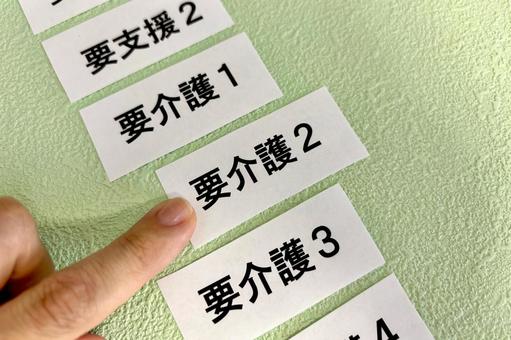
「国保連請求」の流れを理解するためには、介護保険の仕組みを把握しなければなりません。
介護保険とは、介護や支援が必要な方(要介護者・要支援者)に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。介護保険の給付を受けるためには、各自治体の介護保険課に申請するか、地区の包括支援センターに相談します。
介護申請を行うと、健康状態や心身の状態に合わせ要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けます。介護認定を受けた後に、実際に保険サービスを利用するためには、包括支援センター、もしくは居宅介護支援事業所に相談しなければなりません。
介護保険サービスには大きく分けて「在宅系サービス」と「施設系サービス」の2種類あり、それぞれの状況に応じた介護保険のサービスをひと月ごとに受け、その月ごとに給付管理を行い国保連に提出し、審査によって整合性が認められた場合、支払いが行われます。
この時、利用者は自身の負担割合に応じて1~3割の自己負担分を支払います。
国保連請求の流れ

国保連請求を行うためには、利用者に介護保険のサービスを提供する必要があります。実際に国保連に介護報酬を請求するには手順があるため、順番にみていきましょう。
利用者と契約を交わす
「国保連請求」をするためには、利用者にサービスを提供しなければなりません。
まず、居宅サービス事業所は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員からサービス提供の依頼を受けます。居宅サービス事業所は依頼のあった利用者と契約を交わし、介護サービスを提供する準備をします。
この際、利用者の自己負担が何割であるか、介護保険の給付制限は受けていないかなど、請求に関わる情報を収集しておくことで、後の請求業務がスムーズに進みます。
また、介護保険証をチェックし、暫定利用かどうかなども併せて確認してください。正式な要介護認定が出ていないうちは国保連請求が行えず、間違えて提出してしまうと返戻扱いとなるため注意が必要です。
サービス提供後に実績報告を行う
利用者との契約後、実際にサービスを提供するためには、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)から提供票の交付を受けます。その予定に沿って、利用者にサービスを提供します。
もともと予定していたサービス内容から変更になった場合や、介護保険適応外のサービスを提供した場合は、都度介護支援専門員へ報告してください。また、「サービス提供票」の交付を受けた後は加算についてや、担当者会議などで確認していたサービス提供曜日や頻度などを確認します。間違いがあったときは、担当介護支援専門員に確認することで、事前に請求時のミスを防ぐことにつながるでしょう。
サービス提供月が終わったら、翌月初めには居宅介護支援事業所へ「サービス提供票」を交付し、互いに予定と実績を照らし合わせます。
必要書類をそろえて国保連合会へ請求する
居宅サービスが実績を交付し、居宅介護支援事業所と相互に確認した後、国保連請求を行います。
国保連請求は毎月1日から10日までの間に行う必要があり、期日までに提出しなければ給付が受けられません。国保連へ提出する際は、「介護給付費請求書」と「介護給付費明細書」の2つの書類をデータ化して請求しましょう。
提出方法は、原則インターネットでの伝送、もしくはCD‐Rなどの電子媒体です。請求データ提出後、国保連で審査が行われた後、請求の翌月の月末に支払われます。
利用者向けの請求書を作成する
居宅サービス事業所は、国保連請求だけでなく、利用者の自己負担分の請求も行います。
利用者負担はそれぞれの収入によって異なり、1〜3割負担です。利用者の中には、生活保護を受給しているためにサービス費の自己負担がない方や、給付制限を受けていて本来の負担割合よりも高い自己負担額を支払う必要がある方もいるため、請求書作成の際は注意してください。
また、介護保険の更新や区分変更申請などの手続きをし、正式な介護度が決定していない場合は、認定結果が出るまで請求できません。介護度が決まるタイミングによっては、「月遅れ請求」の扱いとなります。
介護報酬の支払いを受ける
居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所それぞれが提出した請求内容に問題がなければ、介護報酬の支払いが行われます。支払われる金額は、事前に「介護給付費等支払決定額通知書」が送られてくるため、内容を確認しておきましょう。
請求内容に不備があった場合は返戻(へんれい)となり、書類の修正や再提出しなければならない場合があります。給付管理票の修正が必要な場合は、居宅支援事業所のケアマネジャーとやり取りして再度請求を行ってください。
国保連請求を行うのに必要な書類

国保連請求をするために必要な書類は、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所で異なります。
特に居宅介護支援事業所は提出する書類も多く、請求時の審査の基準となるため、不備のないようにしなければなりません。審査により、それぞれの書類の整合性が認められて支払いが行われるため、不備がないように注意してください。
ここからは、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所ごとに必要な書類について解説します。
居宅介護支援事業所のケース
居宅介護支援事業所で国保連請求のために必要な書類は、次の3種類です。
- 介護給付費請求書
- 給付管理票総括票
- 給付管理票
上記は書類ごとに介護サービス単位数の内訳を示していたり、利用者の自己負担分の金額を示していたりと、請求に欠かすことのできない書類です。
国保連請求では、居宅介護支援事業所で作成する給付管理表と、居宅サービス事業所で作成する介護給付費明細書を突合し、審査します。
審査の基準となるのは、居宅介護支援事業所が提出する給付管理表です。いくらサービス事業所が正しい請求内容を提出しても、居宅介護支援事業所側が間違った給付管理表を作成してしまうと審査が通らず、サービス事業所に介護給付費が支払われません。
提出する給付管理表は正確に作成しましょう。
居宅サービス事業所のケース
居宅サービス事業所で国保連請求のために必要な書類は、以下の2種類です。
- 介護給付費請求書
- 介護給付費明細書
書類ごとに、利用者へサービスを提供した内訳を示していたり、サービス事業所は利用者への自己負担分の請求も必要なためその金額が記載されていたりと、居宅介護支援事業所とは提出書類が異なります。
居宅介護支援事業所の請求と同様に、サービス提供事業所の保険請求も手作業で行うことは業務負担の増加やミスも生じやすいため、介護ソフトの活用が一般的です。
それぞれの提出書類においては、必要な項目や関係書類は厚生労働省から通知が出ています。下記を確認してください。
参考:厚生労働省「介護給付費請求書等の記載要領について」
厚生労働省「(表)介護給付費請求書等の記載要領について関係資料一式」
国保連請求に関する問い合わせ先について

国保連請求(介護保険請求)をする際、不明な点や確認したい点があるときは、各都道府県に設置されている国保連合会に問い合わせをします。電話の場合、対応は国保連合会が営業している日中のみに限られます。国保連合会の営業時間は事前に確認してください。
また、自治体によってはメールやファクスなど、電話以外での問い合わせも受け付けています。請求時期は電話での問い合わせが混み合う場合も考えられるため、電話以外の問い合わせ方法がある場合は、それらを活用することでスムーズにつながる可能性があるでしょう。
ただし、メールやファクスで問い合わせる場合は、返答までのタイムラグが生じるため、時間に余裕を持って行うよう注意しなければなりません。
国保連請求を行う際に知っておきたいこと

国保連請求(介護保険請求)をする際に、聞き慣れない用語や、その対応に困惑することも少なくありません。国保連請求(介護保険請求)を進めていく上で、事前に知っておくべきポイントがいくつかあるため、解説します。
国保連請求の期間
国保連請求の請求実施期間は、毎月1〜10日の間とされています。11日に請求を提出しても受理されず、介護報酬の支払いを受けられないため注意してください。
また、原則は10日までですが、締切の10日が日曜日や祝日の場合は、休日明けの11日などが締切日になります。締切間際に提出するよりも、余裕を持って請求業務ができるようカレンダーを確認し、事前にスケジュールを組むことが重要です。
サービス提供月から起算して翌々々月の1日から起算した2年間は、請求が可能です。
2年を過ぎると請求時効となり、以降は請求しても報酬は支払われないので、注意しなければなりません。
返戻
返戻とは、請求内容に不備があった場合に請求審査が通らず却下されることを指します。返戻されたからといって、それ以降請求審査が通らないということはなく、返戻内容を確認し、修正後に国保連へ再提出することで支払いが受けられます。
返戻となる理由で多いものとして、給付管理と介護給付費明細書の相違、市区町村の介護認定の相違(正式な介護認定が出る前に請求をかけた場合に多い)、明細書の重複などがあります。
請求審査が通らず返戻となった場合、その月の請求業務に加えて、過去の請求も見直す手間が生じてしまいます。居宅介護支援事業所と細かくやり取りし、可能な限り請求の誤りを減らせるよう努めましょう。
過誤申立
過誤申立とは、国保連請求で行われた審査の結果「請求不備なし」と判断されて支払いが行われた後、請求内容に不備があったと気付いた際に一度請求を取り下げる手続きです。過誤申立は、各自治体に「過誤申立書」を提出してください。
過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の手続きがあります。通常過誤の場合、申請書を提出すると過誤決定通知書が届き、給付費の取り下げが行われます。再請求の必要がある場合は、正しい請求内容を国保連に提出することで、給付が受けられます。
同月過誤の場合、過誤申立と正しい請求内容は同じ月に提出しましょう。同月に手続きすれば、取り下げと再請求の支払いが同時に行われるため差額調整となり、事業所の金銭的負担は軽減されます。ただし、同月過誤は自治体との請求スケジュールを調整する必要があるため、注意が必要です。
月の途中で介護区分が変更になった場合の対応
月の途中で介護度が変更となった場合には、変更前後の介護度に準じて請求しなくてはなりません。
【例】9月20日に介護度が「要介護1」から「要介護2」に変更になった場合
9月19日までは「要介護1」に応じた単位数で請求し、9月20日からは「要介護2」に応じた単位数で請求します。
特に通所介護などの、介護度によって単位数が変化するサービス種別の場合は、変更前後の点数の差異に注意しましょう。また、要支援から要介護へ変更になった場合、介護給付費明細書そのものが異なるため、別々の請求となります。
月遅れ請求のやり方
月遅れ請求とは、通常の請求締切に間に合わなかったり、意図的に提出しなかった請求のことを指し、請求期日の10日までに未提出の請求データに対して行う請求方法です。
主に、利用者の介護認定結果が出る前からサービスを提供した場合や、介護度の変更申請を提出した場合などが理由として挙げられます。他に返戻によって請求が遅れた場合や、利用者の要介護認定の遅れなども月遅れ請求の対象となります。
どのような理由で月遅れ請求の対象としたのかを、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所の両方が把握し、月遅れとした翌月の請求には忘れず提出するようにしましょう。
国保連請求は介護ソフトを導入するのがおすすめ

国保連請求は、単位数の計算やサービスコードの確認、請求書データの作成など、実際に請求を提出して給付を受けるまでに多くの作業が発生します。その全てを手作業で行うことは、業務負担の増加や請求ミスなどを引き起こすことになりかねません。
請求業務の効率化、ミスの軽減に向けて介護ソフトを導入するメリットについて解説します。
請求業務の効率化を図れる
介護ソフトを活用することで、請求業務の効率化が図れます。居宅サービス事業所からの実績など、必要に応じて手入力が必要な場面もありますが、多くの介護ソフトが利用者の基本情報や介護保険情報、サービス提供票などの帳票管理と連動しているため、請求業務にかかる時間を大幅に削減してくれます。
介護事務を配置していない事業所は、ケアマネジャーや事業所で決めた担当者(主に管理者や相談員・支援員など)が請求業務を行っています。請求業務の時間を削減できれば、結果として他の業務をする時間を確保できたり、利用者と関わる時間が増えてケアの質の向上につながったりする可能性があるでしょう。
返戻リスクを軽減できる
介護ソフトは、請求業務の一連の流れの中で不備があった場合に、その内容を通知してくれる機能を備えています。請求を提出する前に間違いに気付くことで、返戻のリスク軽減につながります。
ソフトを活用しない場合、利用者情報の記入や単位数の計算、帳票に実績の転記など、さまざまな請求業務を全て手作業で行うためミスが発生しやすくなり、返戻の可能性が高まります。
国保連請求は、居宅介護支援事業所とサービス提供事業所の請求内容を照らし合わせて審査されます。どちらか一方に間違いが生じると、相互に手間や負担がかかってしまいます。
請求以外にも便利な機能が備わっている
介護ソフトには、請求業務以外にも利用者の台帳管理や各計画書の作成、帳票管理など便利な機能が多く備わっています。介護業界もICT化が徐々に進んできており、請求業務以外にも業務効率化や負担軽減を図ることで、ケアの質の向上につながるでしょう。
まとめ

居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所どちらも提供したサービスの対価として、介護報酬を受け取るためには、国保連請求を正しく行うことが必要です。また、正しく国保連請求を行うことで、事業所の安定した運営や利用者との金銭トラブルの防止などにもつながります。
「まもる君クラウド」では国保連請求をスムーズに行いながら、ミスも減らせるよう請求ソフトを備えています。また、日々の業務に活用できる台帳管理や書類作成にも対応しているので、介護ソフトをまだ導入していない事業所は、ぜひ検討してみてください。