Nursing care
column 介護コラム
LIFE(科学的介護情報システム)のフィードバック活用方法を紹介
投稿日:
LIFE(科学的介護情報システム)は2021年度の報酬改定で創設されました。運用開始から3年がたち、時間の経過とともに周知されてきています。
徐々に浸透しつつあるLIFEですが、フィードバックされた情報は上手に活用できているでしょうか?「活用方法が分からない」「どのタイミングで活用していいか分からない」といった疑問を抱いている介護事業所もあるかもしれません。
今回は、LIFEからフィードバックされた情報の活用方法について解説していきます。
目次
LIFE(科学的介護情報システム)とは?

LIFEとは、全国の介護施設や事業所で記録されている利用者の認知症・栄養・嚥下(えんげ)・口腔(こうくう)などの心身状態や、プランやケアの内容を収集・分析し、結果を事業所へフィードバックするシステムです。
厚生労働省では、以下の点をシステム導入のメリットとして挙げています。
- LIFEに情報提供を行い、フィードバックされたデータを活用することで、利用者に関わる職員が共通の目標に向かって取り組みやすくなること
- 評価が数値でフィードバックされるため、可視化しやすく、計画や行ったケアの内容を見直すPDCAサイクルがスムーズにできること
参考:厚生労働省「科学的介護情報システム (LIFE) スタートガイド」
科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは?

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは、LIFEの運用開始とともに2021年度の介護報酬改定で新たに創設された加算です。フィードバックされた情報を基に、PDCAサイクルの推進や、利用者へ提供するケアの向上を行うことで算定されます。
ここでは、対象サービスや算定要件について解説します。
科学的介護推進体制加算を算定できるサービス
科学的介護推進体制加算の算定対象となるサービスは通所介護や通所リハビリテーション、介護老人福祉施設、介護老人保健施設といった在宅サービスから施設サービスまで多岐にわたります。
<通所・居住・多機能サービス>
- 通所介護
- 通所リハビリテーション(予防含む)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(予防含む)
- 特定施設入居者生活介護(予防含む)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
<施設系サービス>
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
上記の介護サービス事業所は、厚生労働省が設けているLIFEのホームページから利用登録することで、加算を算定できるようになります。
単位数や算定要件
科学的介護推進体制加算は、算定する事業所種別で、単位数や算定要件が一部異なります。施設系サービスでは、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の2種類が設けられていますが、同時算定はできず、どちらか一方のみとなるため注意が必要です。
それぞれの類型別に、単位数、算定要件を見ていきましょう。
通所系・居宅系・多機能サービス
<単位数>
- 40単位/月
<算定要件>
- 入居者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況などに係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
2024年度の報酬改定から、加算算定のための必須項目データの提出は、少なくとも3カ月に1度とされています。提出し忘れることのないように注意が必要です。
介護老人保健施設・介護医療院
【科学的介護推進体制加算(Ⅰ)】
<単位数>
- 40単位/月
<算定要件>
- 入居者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況やその他入居者の心身の状況などに係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたり上記の情報やその他サービスを、適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
【科学的介護推進体制加算(Ⅱ)】
<単位数>
- 60単位/月
<算定要件>
- 入居者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況やその他入居者の心身の状況などに係る基本的な情報に加えて、入居者ごとの疾病状況などの情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたり上記の情報やその他サービスを、適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
介護老人保健施設や介護医療院の科学的介護推進体制加算は、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれます。算定要件の違いは、加算(Ⅱ)は基本的な情報に加えて、疾患や薬事情報などを合わせて提出する必要がある点です。
介護老人福祉施設
【科学的介護推進体制加算(Ⅰ)】
<単位数>
- 40単位/月
<算定要件>
- 入居者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況やその他入居者の心身の状況などに係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたり上記の情報やその他サービスを、適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
【科学的介護推進体制加算(Ⅱ)】
<単位数>
- 50単位/月
<算定要件>
- 入居者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況やその他入居者の心身の状況などに係る基本的な情報に加えて、入居者ごとの疾病および服薬の状況などの情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたり上記の情報やその他サービスを、適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
介護老人福祉施設も、介護老人保健施設などと同様に加算(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれていますが、これは換算(Ⅱ)が50単位/月です。算定要件の違いも同様で、基本情報に加えて疾患や薬事情報などを合わせて提出する必要があります。
LIFEを活用しないと加算算定ができなくなる可能性がある

2021年度の報酬改定では、多くの加算の算定要件にLIFEへのデータの提出、フィードバックの活用が盛り込まれました。介護業界もICT化の促進や、より根拠のあるケアの提供などが求められています。
今後の報酬改定においても、現時点でLIFEの活用が算定要件ではない加算、新設される加算はどれもがLIFEの活用を必須とする可能性もあるため、今後の報酬改定の方向性について注視していかなければなりません。
LIFEを活用したPDCAサイクルのプロセスとは?
LIFE導入の目的のひとつに、フィードバックを受けてPDCAサイクルをよりスムーズにすることが挙げられます。各項目ごとに、どのような目的や方向性で活用すればより効果的か解説します。
C:現状の評価
LIFEにおける利用者の評価は、全国一律の基準によって行われます。
質の高いフィードバックを得るためにも、利用者の評価基準にばらつきがあってはいけません。事業所内で、各職種の代表者を決め、評価方法を確認。その後、特定の職員だけが評価を実施するのではなく、全職員が一律の判断基準で評価できるよう事業所内で研修や勉強会を開催します。
事業所全体、職員のケアの向上のためには、全国一律の基準を用いて、客観的な評価を受けそれを把握することが重要です。
A:計画の見直し
フィードバックを受けた内容をもとに、計画の見直しを行います。この時、事業所の管理者や少数の職員で、フィードバックされた内容についてついて話し合うのではなく、事業所全体でディスカッションし、課題はなにかを共有することが重要です。
また、この時に不足していた点ばかりではなく、改善した点についても共有することで、職員のモチベーションを保ち、次の課題解決に向けてより意欲的に計画を見直せます。
P:課題の整理と目標の設定
フィードバックの内容をもとに、抽出し共有した課題が利用者個人に関わる課題なのか、事業所としての課題なのかを整理します。
課題を整理した後は、目標を設定します。目標も職員間で共有し、各々が納得できるものに設定することが重要です。設定した目標に、いつまで、誰が、なにを、どのように行うのかも明確にすることで、役割がはっきりとします。
また目標を設定する際も、「次のフィードバックを受けるまで」や「半年間」など期間を設けることで、目標達成のためにより段階を踏んで取り組めます。
D:計画にもとづいた取り組みの実践
立案した計画にもとづいて、取り組みを実践していきます。実践途中で、疑問点や計画通りに取り組めないことなど、さまざまな問題が生じる可能性があります。そのような計画実践の課題、気づきをそのままにせず、職員間で共有することが重要です。
また、すぐに結果を求めるのではなく、提供するケアの内容をどのように変え、それによって利用者にどのような変化が生じたかを継続して観察し、その結果を積み重ねていくことが大切です。
LIFEのフィードバック活用を広める方法

LIFEをデータの提出のみで終わらせることなく、ケアの質の向上や業務改善へとつなげていくには、フィードバックをいかに有効活用できるかが重要です。
ここからは、フィードバックの活用方法、タイミングについて解説します。
会議で共有する
フィードバックされたデータは、利用者自身やその家族、支援に携わるサービス事業所や専門職種間が集まる担当者会議で共有できます。利用者自身が自分の状態を客観的に把握することや、家族もその情報を共有することで、ケアプランの目標達成のためにセルフケア、インフォーマルサービスとして何をすべきなのかより明確になります。
また、事業所間・専門職種間でデータを共有することは、利用者の状態像のずれを補正したり、情報の解釈を統一化し、ケアの方向性や手法のばらつきをなくすことにつながります。寝たきり状態で、多くの介助を要する利用者や、医療的なケアを必要とする利用者など、数多くの支援者が介入するケースほど、このフィードバックの共有は重要になってくるでしょう。
さらには、通所リハビリテーション事業所で開催される「リハビリテーション会議」でも、データの共有と活用による効果を期待できます。リハビリテーション会議は身体状況や、リハビリをより効果的に行うためのケアについて話し合うことから、担当者会議よりも的を絞った内容で話を深めていけます。
フィードバックされたデータを、より専門的かつ詳細に共有し解釈し、リハビリの提供へとつなげていくため、利用者や家族も訓練の効果をより感じられるでしょう。
科学的介護提供体制加算の評価シートを活用する
LIFEからフィードバックされる情報は、事業所ごとのデータと利用者ごとのデータの2種類あります。全国平均と比べて、自らの事業所はどのような位置にあるのかを数値として見て、客観的に捉えられます。
例えば、自事業所の平均要介護度が全国平均と比べて高い場合、自立支援に向けたケアが不足している可能性があると考えられます。また、ADL(日常生活動作)の維持・改善の割合が平均よりも高い数値だった場合、利用者に質の良いケアを提供できていた証となり、どのようなケア方法がよかったのか、さらにケアの質を高めていくためにどのような対応をとるべきなのか、次のステップに進めるでしょう。
このように、フィードバックされた評価の内容を事業所でも分析し、その結果を職員間で共有することで、事業所としての目標を掲げ取り組むことにつながります。
個人別の評価シートを活用する
利用者ごとのフィードバックされた評価は、個別ケアにより一層生かしていけます。過去の評価と比較して、現在の利用者の状態を把握することが重要です。
利用者は高齢のため、新たな疾患を患ったり、骨折などによる急激なADLの変化がない限り、大きく状態が変化することは頻繁には見られません。その中でも歩行状態や、認知機能の状態、嚥下機能の状態など、それぞれの項目に焦点を当てて経過を追うことで、ささいな変化にも早期に気づき、機能低下予防や維持に向けたプログラムを組むことができます。
また、個別の評価を多職種で共有し、検討することで多角的に利用者を捉えることも、評価シートを活用する上で重要なポイントです。
科学的介護情報システム(LIFE)を導入するメリット

LIFEには、全国の介護事業所から利用者に関するさまざまな情報が蓄積・分析されています。LIFEを活用することで、事業所にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
利用者に合わせたケアを提供しやすくなる
従来の介護現場では、利用者の状態を数値化し客観的に評価することが難しいとされてきました。利用者の表情や態度の変化、反応の変化など、感覚的なものに頼ることが多く、その判断もケアを提供するスタッフの経験や知識・技術によって差が生じていて、長年の課題とされてきた経緯があります。
経験や感覚ではなく、フィードバックされた利用者の情報に基づきケアを提供することは、一人ひとり個別性のあるケアを提供することにつながります。また、自分自身に合った介護を受けることで、利用者の自立支援の促進や重度化予防なども図れるでしょう。
業務の改善を図れる
LIFEからのフィードバックのデータには、事業所ごとの情報も含まれています。今まで自分たちの事業所の中だけでのみ判断していたケアの内容や、事業所の体制を全国のデータと照らし合わせて比較ができます。
事業所の特徴や、不足している点など、フィードバックされた情報を自分たちで分析し、業務やケアの見直し・改善へとつなげられるでしょう。業務内容を改善することで職員にも余裕が生まれ、利用者とコミュニケーションを取る時間が増えたり、ケース記録の時間に回せたりと、相乗効果が図れる可能性もあります。
科学的介護推進体制加算を取れる
LIFEの導入は、事業所の収益の増加を図ることができるのもメリットの1つです。
前述で述べたように、算定要件を満たすと40単位/月~60単位/月の加算を算定できます。これは事業所加算ではなく、個人加算のため利用者一人ひとりに算定できるものです。
利用者の上限数はそれぞれ事業所の規模ごとに定められていますが、算定に向けて積極的に取り組むことで、利用者だけでなく、事業所にもプラスの影響を与えることになります。
科学的介護情報システム(LIFE)を導入するデメリット
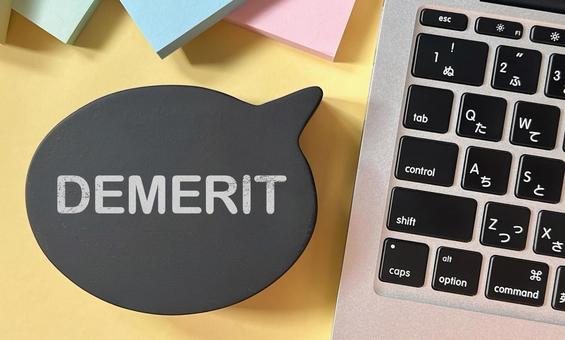
LIFEを導入する際、メリットだけでなくデメリットも生じる可能性があります。利用者と事業所どちらも良い側面ばかりを求めて導入した結果、データの提出やフィードバックの活用がなされていなければ、本末転倒となりかねません。
代表的なデメリットについて解説します。
業務量が増える
加算を算定するためには、LIFEのホームページに直接データを入力する、もしくはLIFEと連動している介護ソフトに入力した後、それを出力しなくてはなりません。どちらの方法を選択しても、加算算定前後では「データの入力」という新しい業務が増えることとなります。
LIFEの活用に限ったことではなく、従来よりも業務量が増えるのは、面倒と感じる職員も少なくありません。また、フィードバックを受けた内容を活用することができなければ、ただデータを入力する手間だけが増え、なおさら負担を感じてしまう可能性があります。
データの提出だけで終わらず、フィードバックをしっかりと行うことが重要です。
加算算定によって利用者の金銭的負担が増える
科学的介護推進体制加算を算定することで、利用者の自己負担額は増えることになります。単位数にすると40〜60単位/月ですが、1割の利用者で400〜600円(〜3割負担の方は割合に応じて変化)の増加です。
個別機能訓練加算や口腔機能向上加算のような、利用者自身の希望や状態に応じて算定するものであれば、同意を得られやすく、利用者自身も変化を感じやすいでしょう。しかし、科学的介護推進加算のように利用者自身が加算算定による変化を感じにくい場合、同意を得ることが難しい可能性があります。
そのため、加算の説明は必要性をしっかりと説明し、同意を得ることが重要です。
まとめ
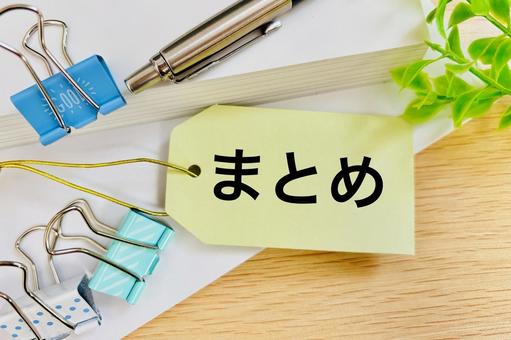
LIFEのフィードバックをうまく活用することで、利用者と事業所相互にメリットがあります。データの提出のみで終わらせてしまわないよう、今回の記事で紹介した活用方法やタイミングを参考に、これからの日々の業務に生かしてください。