Nursing care
column 介護コラム
居宅介護支援(ケアマネージャ)ソフトの選び方6つのポイントを解説!
投稿日:
ケアマネージャーはアセスメントやケアプランなど様々な書類業務を行いますが、これらの業務は居宅介護支援ソフトを活用することで効率化を図ることができます。
しかし居宅介護支援ソフトは、ソフト会社によって対応している機能や料金形態が異なるため、自事業所に適したソフトを選定する必要があります。
本記事では居宅介護支援ソフトの機能や導入までの流れや、選び方のポイントについて分かりやすく解説しています。是非参考にしてみてください。
居宅介護支援ソフトとは?

介護ソフトは介護サービスに合わせて機能が異なっています。
居宅介護支援ソフトとは「居宅介護支援事業所」に特化した介護ソフトで、利用者情報の管理や介護保険の請求に加え、アセスメント、ケアプランの作成などケアマネージャーが必要とする機能が備わっているソフトです。
ケアマネージャーは他の介護サービスに比べても書類業務が多く、業務負担が大きくなるという声をよく聞きます。居宅介護支援ソフトを導入することで、手での転記作業や紙での書類管理を全てソフト内で行うことができ、書類務負担の軽減に繋げることができます。
居宅介護支援ソフトの主な機能
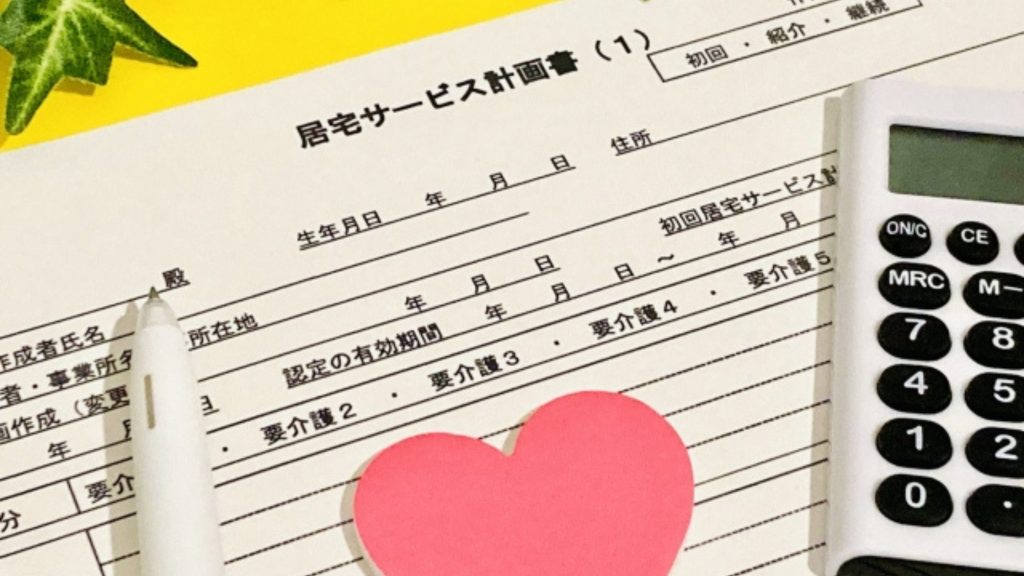
こちらでは、居宅介護支援ソフトが対応している主な機能をまとめています。ソフト会社によっては一部のみ対応している物もあれば、一気通貫で管理できるソフトもあります。
まずは居宅介護支援ソフトでどのような事ができるのかを把握しましょう。
利用者情報管理
利用者氏名、生年月日、住所、連絡先などの基本情報から、要介護度、認定有効期間、区分支給限度基準額など介護保険証の情報を管理できます。
ソフトによっては利用者ごとに担当のケアマネージャーを設定することも出来るので、ケアマネージャーを複数抱える居宅介護支援事業所では、そういった設定が可能か確認すると良いでしょう。
アセスメント作成
利用者の相談内容やご家族の希望、利用者を取り巻く環境、介護サービスの利用状況、健康状態など、介護サービスを提供する上で必要となるアセスメントを作成できます。過去に作成したアセスメントもソフトに保存されているため、紙での管理が必要なくなります。
また、居宅介護支援ソフトによっては複製機能もあるため、アセスメントの更新の際でも、前回内容をコピーして新たに作成することも出来ます。
アセスメントの様式はソフトによって異なり、全国社会福祉協議会の「居宅サービス計画ガイドライン」や「MDS方式」、「簡易アセスメント」など様々です。現在使用しているアセスメントがある場合は、同じ様式に対応している居宅介護支援ソフトを検討すると良いでしょう。
ケアプラン作成
ケアプラン第1表から第7表までの作成機能です。ケアプランに対応している居宅介護支援ソフトであれば、第1表から第7表まで全て作成できることがほとんどです。また、シンプルな作成機能のほかに、他帳票からの連動機能や複製機能などを有しているソフトもあります。
例えば、第2表で作成した短期目標をモニタリングシートに連動させることができ、同じ項目を何度も入力する手間を省くことが可能です。ケアプラン作成にかかる作業時間の短縮や、転記による記載ミスを減らしたい場合は、このような機能のある居宅介護支援ソフトがおすすめです。
モニタリング作成
ケアマネージャーが毎月作成するモニタリングシートを管理する機能です。居宅介護支援事業所のケアマネージャーは1カ月に1回、ケアプランで決めた目標に対する達成度や、利用者、家族の満足度などをモニタリングする必要があります。
モニタリング作成機能では、それらの内容をシステム上で作成、管理することができます。また、第2表で作成した目標を連動することができるソフトもあるため、作成にかかわる作業を短縮することも可能です。
給付管理
利用者の月間のスケジュールを元に単位数の合計や、利用者負担額などを管理することができます。また、区分支給限度基準額が設定されている居宅介護支援ソフトでは、限度額を超過していないかも合わせて管理することができます。
給付管理は利用者への請求額や、国保連合会への介護保険請求に関わってくる非常に重要な業務です。居宅介護支援ソフトで管理することで、計算間違いなどの人為的ミスを減らすことができます。
ケアプランデータ連携システム
国保中央会の提供するケアプランデータ連携システムを利用するためには、それに対応している居宅介護支援ソフトを利用する必要があります。
居宅介護支援ソフトの中には、同ソフト内での連動が可能なケースもありますが、これらの機能では他社ソフトとの連携ができないといったデメリットもあります。
ケアプランデータ連携システムなら、対応しているソフト間であればどのソフトでもデータの連携が可能です。また「居宅介護支援費Ⅱ」の算定要件には「ケアプランデータ連携システムの活用」が含まれており、システムの利用が必須となっています。
介護保険請求
居宅介護支援事業所が介護保険請求を行う際に必要となる「給付管理表」と「介護給付費明細書」の作成機能です。居宅介護支援ソフトの中には、この請求機能のみ対応している場合があり、アセスメントやケアプランの作成に対応していない場合もあります。
また、国保連への伝送機能は、伝送ソフトの導入が別に必要となるケースもあります。
居宅介護支援ソフトの選び方6つのポイント

居宅介護支援事業所で業務効率化を図るためには、事業所にあったソフトを選定する必要があります。例えば、多機能なソフトを導入しても、ケアマネージャーがそれらの機能を使いこなせなければ、余分なコストだけが掛かってしまいます。
こちらでは居宅介護支援事業所が最適なソフトを選ぶためのポイントを6つに分けて解説しています。選定の際の参考にしてみてください。
①必要な機能を網羅しているか
居宅介護支援ソフトによって対応している機能は様々です。まずは事業所がどのような課題を抱えているのかを洗い出し、それに対してどういった機能が必要なのかを明確にしましょう。
また、複数のソフトを導入することで、あらゆる業務に対応することが可能ですが、その分ランニングコストが大きくなったり、管理が煩雑になったりと、かえって業務に支障をきたす場合があります。極力ひとつのソフトで、必要な機能が網羅されていることが望ましいです。
②システム料金が予算内に収まっているか
居宅介護支援ソフトの料金形態は様々ですが、基本的には毎月のランニングコストが必要となります。あらかじめ予算が決まっている場合はシステム料金が予算内に収まっているのかを確認しましょう。
ソフトの相場は月額約5,000円〜数万円と幅はありますが、極端に安価なソフトの場合、介護保険請求しか出来ないなど、一部機能にしか対応していない場合もあります。逆に高額なソフトだと機能が豊富です。しかしケアマネージャーや管理者が使いこなせず、費用対効果が悪くなるケースもあるため、機能と料金のバランスを見ながら、最適な予算を設定しましょう。
③ケアプランデータ連携システムに対応しているか
ケアプランデータ連携システムへの対応も、居宅介護支援事業所にとっては重要な選定のポイントになります。令和5年4月より、厚生労働省が介護現場のデジタル化を進める事を目的とし、「ケアプランデータ連携システム」の運用を開始しました。
昨今、ケアプランや実績情報など、介護支援事業所とサービス事業所とのやり取りは、郵送やFAXなどの紙媒体が主流となっていますが、ケアプランデータ連携システムを活用することで、ネット上で書類のやり取りが可能になります。
しかし、連携システムを運用するためには、双方が対応しているソフトを導入している必要があります。また、令和6年の法改定により「居宅介護支援費Ⅱ」の算定要件に「ケアプランデータ連携システムの活用」が含まれるなど、連携システムの活用が推奨されています。
今後さらにケアプランデータ連携システムの活用が推奨されていくため、対応の有無についてはしっかりと確認しておきましょう。
④法改定時の対応スピード
介護報酬改定の際にソフト会社側の対応スピードも重要な選定ポイントです。改定のタイミングは3年に一度の4月に行われることが多いですが、ケアマネージャーはそれより前の3月には利用票を作成しておく必要があります。
しかし、居宅介護支援ソフトがいつ対応するのかは、ソフト会社によって異なります。対応が遅れている場合、ケアマネージャーは提供票を作成することができず、利用者やサービス事業所側にも影響してしまいます。
介護報酬改定への対応スピードは直接ソフト会社に問い合わせるか、もしくはJAHISに加盟しているのかを基準に選定をするといいでしょう。
JAHISとは?
保健、医療、福祉分野の情報システムを扱う会員企業で構成される工業会です。 情報システムの導入やシステム間接続を円滑に行うための標準化の推進や品質向上への取り組みを通じて、業界のみならず医療機関様、保健福祉事業者様、患者様にとっての利益向上にも広く貢献する活動を推進しています。
引用元:一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
⑤クラウドタイプのソフトか
居宅介護支援ソフトには大きく分けて「パッケージタイプ」と「クラウドタイプ」の二つに分けられます。
パッケージタイプのソフトは、パソコンへソフトをインストールする事で運用することができます。そのため、操作が行えるのはインストールのされているパソコンのみで、別のパソコンや外出先から操作することができません。
クラウドタイプのソフトとは、インターネットを介して運用することができるソフトの事で、パソコンへのインストールは不要です。インターネット環境があればどこからでも操作が可能なため、複数のパソコンや外出先、スマホ、タブレットからでも操作が可能です。
ケアマネージャーを複数抱える居宅介護支援事業所や、利用者宅などの外出先でもソフトの利用を考えている場合は、クラウドタイプのソフトがおすすめです。
⑥導入後のサポートは充実しているか
ほとんどのソフト会社は導入後でも、何かしらの形でサポートを行っていますが、対応方法や対応スピードはソフト会社によって様々です。特に毎月1日~10日までの請求期間は、ソフト会社への問い合わせが集中しやすく、電話をしてもなかなか繋がらないといった事も考えられます。
そのため、可能であれば導入前にサポートセンターへの繋がりやすさや、返答の質を確かめておくといいでしょう。導入前に確認ができない場合は、口コミサイトなどで実際に利用している事業所の声を元に検討することをおすすめします。
居宅介護支援ソフトを導入までの流れ
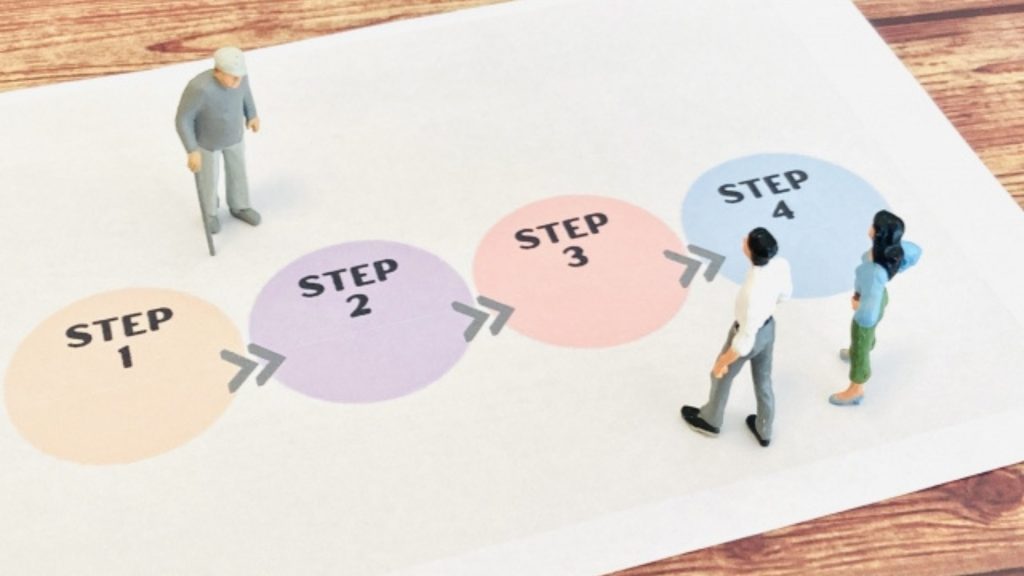
基本的な導入の流れをまとめています。複数社を同時に検討することも出来ますが、時間やケアマネージャーの負担を考えると、1~3社ほどに留めるといいでしょう。
資料請求などで情報収集をする
まずは、各社への資料請求や問い合わせなどで情報収集をしましょう。既に求めている機能や、予算が決まっている場合はそれを基準に検討を進められますが、まだどういったソフトがあるのか分からないといった状況であれば、「紙での管理を減らしたい」「ケアマネージャーのテレワークに対応したい」など、抱える課題を軸に検討を進めましょう。
デモンストレーションや無料体験を受ける
ソフト会社が無料体験やデモンストレーションを行っている場合は、使用感や操作性を確認しましょう。実際に操作を行うケアマネージャーが複数名いる場合は、それぞれにソフトを操作してもらい、最も使い勝手の良いソフトを選定することで、導入後のミスマッチを減らすことができます。
また、この期間中にカスタマーセンターへ問い合わせを行うことで、電話の繋がりやすさや回答の質を見極めることができます。導入後の事を想定し積極的に活用しましょう。
見積もりをとる
ソフト会社によってはシステム利用料以外にもバージョンアップ費用や保守費用、サポート費用が別途必要になる場合があります。導入前には各社の見積もりを取り、料金の内訳について把握しておきましょう。
居宅介護支援ソフトなら介護ソフト「まもる君クラウド」がおすすめ

必要な機能が一気通貫で管理でき、低価格な居宅介護支援ソフトを探している方には、介護ソフト「まもる君クラウド」がおすすめです。まもる君クラウドが選ばれる理由は以下の4つです
必要な機能を全て網羅
アセスメントからケアプラン、サービスの予定実績管理、介護保険請求などケアマネージャーが必要とする機能を全て網羅しています。またケアプランデータ連携システムにも完全対応しており、全てのデータをまもる君一つで一元管理していただけます。
その他にも、居宅介護支援事業所のお声を元に生まれた機能が複数あるため、是非一度詳しい内容を確認してみてください。
初期費用0円、月額7,800円の低価格
まもる君では、初期費用や保守費用を一切いただかず、月額7,800円のみで運用していただけます。またクラウドタイプのソフトなためパソコンの台数制限がなく、外出先やスマートフォン、タブレットからでも操作可能です。
不慣れな職員でも安心の操作性
まもる君は、シンプルな画面と直感的な操作性が特徴で、高齢なケアマネージャーや、初めてソフトを利用する方でも簡単に運用していただけます。
満足度の高いカスタマーセンター
まもる君に関する質問はもちろん、返戻対応や請求業務なども、介護業界に精通したスタッフが徹底的にサポートをいたします。対応スピードについても好評いただいております。
まとめ
居宅介護支援ソフトは、ソフト会社によって対応している機能や料金形態は様々です。まずは自事業所の課題をしっかりと把握したうえで、最適な居宅介護支援ソフトを選定する必要があります。
また、アセスメントやケアプランといった基本的な機能のほかにも、ケアプランデータ連携システムや介護報酬改定時の対応スピードにも注意して検討するといいでしょう。