Nursing care
column 介護コラム
介護記録を電子化するメリットやデメリットは?ICT化の始め方も紹介
投稿日:
近年、介護業界においてもICTやDXといった言葉を耳にする機会が増えました。しかし、スタッフの平均年齢の高齢化もあってか、アナログな記録方式からなかなか抜け出せない事業所も多いでしょう。
この記事では、実際に介護事業所でICT担当者として介護記録の電子化をした筆者が自身の経験を基に、介護記録を電子化するメリットとデメリット、および成功するためのコツを伝えます。
介護記録のICT化に取り組む必要性

介護記録を電子化する一番の目的は、記録業務の効率化です。記録業務が効率化されると、スタッフの事務作業負担の軽減になります。事務作業時間が減ると、間接業務時間の削減につながり、利用者へ直接ケアをする時間が増えるでしょう。その結果、ケアの質が向上するだけでなく、人材不足の解消が図れるといわれています。
「2025年問題」を間近に控え、国民の5人に1人が後期高齢者となるといわれています。しかし、介護業界はまだ人手が足りません。このことからも、人材不足の解消につながる介護記録のICT化は今後必須となるでしょう。
介護記録を電子化するメリット

厚生労働省の「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」によると、介護記録を電子化するメリットには以下のものが挙げられます。
- 文書作成の時間が短くなった
- 入力済みの情報を他の文書でも利用できるようになった
- 情報共有がしやすくなった
- 全体の業務量が減った
具体的な数字を上げながら、メリットの内容を紹介します。
参考:厚生労働省「介護テクノロジーの導入に関する補助について ICT導入支援事業効果報告 令和3年度導入効果報告まとめ」
業務の効率化を図れる
介護記録を電子化する最大のメリットは、業務の効率化を図れるという点です。厚生労働省によると、令和3年度のICT導入支援事業の補助を受けた5,058の事業所のうち、下記の内容において「業務の効率化が図れた」との報告が上がっています。
| 効果を感じた事業所の割合 | |
|---|---|
| 入力済みの情報を他の文書でも利用できるようになった | 84.8% |
| 文書作成の時間が短くなった | 81.9% |
| 過去の文書(データ)の検索性が向上した | 72.4% |
| 全体の業務量が減った | 68.5% |
また、「間接業務の時間が削減され、直接業務の時間が増加した」との報告も上がっており、数字としても介護記録の電子化によって効率的に業務が行えるようになったことを示しています。
| 削減した間接業務時間 | 増加した直接業務時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年目(※1) | 2年目(※2) | 1年目(※1) | 2年目(※2) | |
| 0〜30分 | 28.3% | 28.5% | 23.4% | 27.5% |
| 30〜60分 | 24.4% | 27.5% | 13.1% | 15.2% |
| 60〜90分 | 7.3% | 10.9% | 3.4% | 5.8% |
※1 令和3年度からICT導入支援事業を受けた事業所の回答割合
※2 令和2年度からICT導入支援事業を受けた事業所の回答割合
スタッフ間でスムーズに情報共有ができる
介護記録を電子化するメリットの2つ目に、スタッフ間でスムーズに情報共有ができるようになることです。
令和3年度の「ICT導入支援事業」を受けた5,058事業所のうち、情報共有に関する導入効果を感じている事業所は以下の通りです。
| 情報共有の回答例 | 効果を感じた事業所の割合 |
|---|---|
| 情報共有がしやすくなった | 90.3% |
| 事業所内の情報共有が円滑になった(話し合い時間の増など) | 88.0% |
| 職場以外でも情報を確認することができるようになった | 47.7% |
手書きで申し送りをする場合は「文字が見にくい」という問題も発生しそうですが、ICT機器で入力すれば読みにくいということはありません。その点からも、スムーズな情報共有が可能となるでしょう。
働き方改革にもつながる
介護記録を電子化するメリットの3つ目は、「働き方改革にもつながる」という点です。介護記録の電子化によって削減された間接業務時間は、利用者をケアする直接業務時間に充てるだけでなく、残業時間の削減や休憩時間の増加につながっているという報告が上がっています。
- 書類業務はサービス残業で行う
- 利用者と一緒に食事を取る時間は「休憩時間」に含まれる
- 休憩時間に食事介助が発生する
上記のようなことがまだ聞かれる介護業界ですが、介護記録の電子化は定時での帰宅が可能となるため、働き方改革にもつながるでしょう。
介護記録を電子化するデメリット
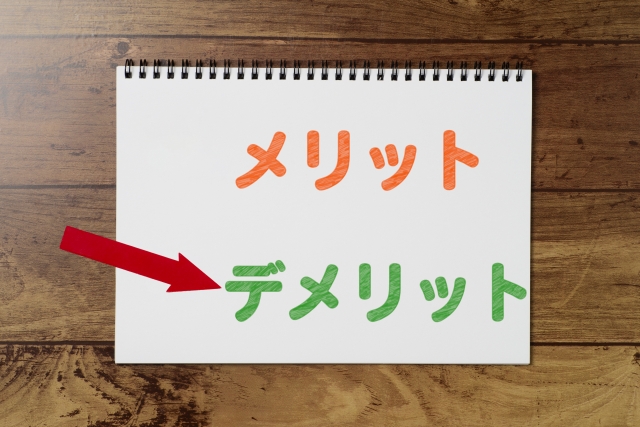
介護施設に勤めるスタッフは、手書きの介護記録に慣れており、パソコンでの入力に苦手意識を持っているスタッフも少なくありません。ここからは、筆者が実際に事業所にICT機器導入担当者として体感した、介護記録を電子化するデメリットについて伝えます。
使いこなすまで時間がかかる
介護記録を電子化する上での一番のデメリットは、使いこなすまで時間がかかるという点です。
厚生労働省の「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」によると、「パソコンやソフトに対する職員の苦手意識の解消、職員への研修等」に課題があると感じている事業所は89.5%ありました。
スタッフの平均年齢が高齢化している介護現場では、日常的にパソコンに触れる機会が少ないあるいは、ほとんどないことから、パソコンなどのICT機器の操作が苦手だと感じているスタッフが多くいることは珍しくありません。パソコンの操作方法から覚えなければならない場合もあり、記録の入力にかえって手間がかかってしまう可能性もあるでしょう。
情報漏えいや不正アクセスのリスクが伴う
介護記録を電子化する上でのデメリット2つ目は、情報漏えいや不正アクセスのリスクが伴うという点です。
スタッフの平均年齢が高齢化している介護業界では、パソコンやICT機器の操作に苦手意識を持つスタッフが多いケースも珍しくありません。ITリテラシーの低さは、情報漏えいや不正アクセスのリスクに直結します。個人情報やプライバシーへの配慮が希薄になってしまう危険性も、課題として挙げられているため、ITリテラシーとセキュリティーの意識を高める必要性があるでしょう。
社内ネットワークには私物のスマートフォンを接続しない、新たにセキュリティーソフトを購入するなど、ルールを定めることも検討ください。
システムを導入するのにコストがかかる
介護記録を電子化する上でのデメリットには、システムを導入するのにコストがかかるという点も見逃せません。厚生労働省の「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」には、パソコンやソフト、システムなどの導入のための費用補助について、89.8%の事業所が課題と感じていると報告されています。
システム導入するための費用には、介護ソフトだけでなくパソコンやタブレット、スマートフォンの購入費用や通信費も含まれます。
ICTに精通した人材を確保しなくてはならない
介護記録を電子化する際には、ICTに精通した人材の確保が重要です。すでに事業所内にパソコンやICT機器に詳しい人材がいれば問題ありませんが、いない場合はITスキルを持つ人材を採用したり、育成したりしてからでないと、介護記録の電子化を円滑に進めることは困難でしょう。
人材の確保ができない場合には、介護ソフトを販売する会社の営業に協力を仰ぐことも必要です。その場合には、事業所スタッフの意向に沿った形でのICT導入ができるよう、事業所の人間が主導権を握るようにしてください。
介護記録の電子化を始める手順

介護記録の電子化を始めるには、以下の手順で実施するとスムーズに使えるようになります。
- ICTの導入計画を策定する
- ICT機器を選定する
- ICT化に伴う業務のプロセスを見直す
- ICT機器の運用体制を整える
- スタッフに研修を行う
- 電子化の効果を検証する
順番に説明します。
1. ICTの導入計画を策定する
介護記録の電子化を進めるためには、まずはICTの導入計画を策定してください。この段階では、介護記録を電子化する目的や導入後に得られる効果の見込み、業務においてどのように活用するかなどを決定します。
ICT機器に慣れていない介護スタッフにとって、どのように導入計画が進んでいくか明確でないと、不安が大きくなってしまいます。ICT導入後に具体的な業務内容の見直しも必要となり、大きな負担をかける可能性があります。
まずは現場の介護スタッフとも共有しながら、導入計画を綿密に立てることが、成功への鍵となるでしょう。
2. ICT機器を選定する
2つ目の手順は、ICT機器の選定です。介護記録を電子化するに至った経緯から自事業所のどこに課題があるかを洗い出し、その課題に合った、かつ課題を解決し得るICT機器の選定が必要です。
ICT機器の選定には、自事業所の環境やスタッフに合った機器を選ぶことが重要です。ICT機器は決して安い投資ではないため、事業所の環境に合わなかったり現場のスタッフがうまく使えなかったりしては介護記録の電子化が失敗に終わってしまう危険性があります。
ICT機器の性能や価格だけを見るのではなく、事業所の環境や使い心地を考慮して選定しましょう。
3. ICT化に伴う業務のプロセスを見直す
介護記録を電子化し、事業所にICT機器を導入する際には、必ず業務のプロセスを見直してください。
介護記録が手書きでなくなると、今まで行っていた業務から不要となる業務が出てきます。一方で電子化したからこそ、今までは必要ではなかった業務が出てくるかもしれません。現在行っている業務を全て洗い出し、ICT機器の導入後に想定される業務と見比べながら、業務のプロセスを見直すことが大切です。
ICT機器の導入は間接業務の時間を削減し、利用者と関わる時間である直接業務の時間を増加させるというデータも出ています。その点を踏まえて業務のプロセスを検討すると、より良いサービスが提供できるでしょう。
4. ICT機器の運用体制を整える
ICT機器を導入し、介護記録を電子化する際には、ICT機器の運用体制を整えることも重要です。
運用体制を整えるとは、具体的に下記を指します。
- ICT機器を管理する担当者を選定する
- 介護記録の電子化に必要な機器や環境を整備する
実際には担当者だけでは進められない場合もあるため、チームを組めるとより良いでしょう。
5. スタッフに研修を行う
ICT機器を導入し介護記録を電子化する際には、現場のスタッフへの研修も必須です。
ICT機器を業務として活用する以上は、現場のスタッフがICT機器を使いこなせなければ電子化の効果も得られません。しかし介護現場のスタッフの平均年齢が高齢化している事業所も多く、ICT機器の使用が定着しにくい傾向にあります。
導入前はもちろん、導入後にも定期的に研修を行うことで、スタッフが安心してICT機器を使えるよう環境を整えましょう。
6. 電子化の効果を検証する
介護記録の電子化は、導入して終わりではありません。導入後には定期的に効果を検証して、うまく使いこなせているかを確認するのが重要です。もし運用がうまくいっていない場合にはその原因を早めに追求して、改善方法を検討する必要があります。また順調に運用できている場合には、不要となった業務が見えてくる可能性もあるでしょう。
介護記録電子化の効果を定期的に検証し、都度改善することで、さらなる業務改善が見込めます。PDCAサイクルとしてうまく回していきましょう。
介護記録の電子化を成功させるためのコツ

ここからは、介護記録の電子化を成功させるためのコツを伝えます。
具体的には、以下のポイントを抑えてください。
- 利用者家族など関係者の理解を得る
- スタッフへの研修期間を長めに確保する
- 分かりやすいマニュアルを作成する
具体的に説明します。
利用者家族など関係者の理解を得る
介護記録を電子化する場合には、事前に利用者家族や関係事業所などの理解を得ることが大切です。
特にデイサービスやショートステイなど在宅介護を支える事業所が介護記録を電子化すると、連絡帳など記録の様式が変更されます。情報共有のツールが変更されるため、導入前には記載されていた情報が記載されなくなることが起こり得ます。様式の見方が変わるため、戸惑う方もいるでしょう。
理解を得るためにも、様式の見本を事前に利用者家族に見せるなども検討してください。
スタッフへの研修期間を長めに確保する
介護記録を電子化するためには、スタッフへの研修期間を長めに確保することも必要です。
現場で働くスタッフは、平均年齢が高齢化している事業所も多くICT機器に不慣れであることが予想されます。最新の機器を導入しても、現場スタッフが使いこなせなければ介護記録の電子化は成功とはいえません。スタッフの中で研修担当者を決めてもよいですが、介護ソフトのメーカーから担当者を招いて研修するのも有効です。
また導入するICT機器によっては、無料のお試し期間を設けているメーカーもあります。現場で実際にICT機器を活用しながらの研修ができるため、トライアル期間をうまく使いましょう。
分かりやすいマニュアルを作成する
介護記録を電子化する際には、分かりやすいマニュアルを作成してください。
介護現場は相手が人であるためか、マニュアルが整備されていない事業所が少なくありません。しかしソフトを使って介護記録を作成する場合、相手が機器であることから、基本的には臨機応変な対応は不要です。
マニュアルを作成すれば、ICT機器の使用に不安のあるスタッフでも記録の入力が容易となります。新人職員や、最近増えている外国人スタッフでも理解できるマニュアルをつくることで、誰もがICT機器を使いこなせるような環境を整えましょう。
まとめ

この記事では、介護記録を電子化するための流れやコツを、メリット・デメリットとともに紹介しました。
厚生労働省の「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」にもあるように、ICT機器の導入は利用者へのケアの質の向上につながります。しかしスタッフの平均年齢が高齢化している事業所にとっては、現状維持バイアスも働きなかなか導入に踏み切れないことでしょう。
ICT機器の操作に不安を感じているスタッフが多い事業所には、60日間無料で試せる介護ソフト「まもる君クラウド」をおすすめします。導入後のサポートも充実しているため、ぜひ検討してください。